未知のウィルスに翻弄されている世界。感染回避と共に心を守るべき!未曾有の混乱に飲み込まれないために。 和久わくこ
和久わくこ
「得体の知れないたんぱく質」との共生
ここまでのながれコロナ不安を自己調整でやり過ごす
決めるのは自分
感染予防をしつつ「やってもいいこと」を決めるのは、自分しかできない。
だって、専門家は超安全策しか口にできない(たとえ不本意でも)のだから。
これが、私が得た結論です。
学生時代に学んだこと、自分の経験、このコロナ禍で新たに学んだことをもとに、たどり着いたことです。
そこに至る道筋は、以下の通りです。
二極化イメージからの脱却
まず、イメージの再確認をしました。
というのは、外部との遮断にこだわってしまうと、清い(はず)の自分と、生理的嫌悪を伴う外部の二極化が進んでしまうからです。
手の皮がすりむけても、手洗いを続けるなど、病んだ状態になりかねません。
だから、再度確認が必要だと思ったのです。
得体の知れないたんぱく質
そのイメージとは。
そもそも私たちは、「得体の知れないたんぱく質」と共に生きている。

菌だったりウィルスだったり、その他だったり、いずれにしろ目に見えないサイズ。
自分自身の身体の中も同様。それは、善玉もあれば悪玉もある。
積極的に取り入れている乳酸菌もあれば、速攻排除すべき病原菌が入ることもある。
日々耐性づくり
健康増進のためによく言われる、「一日一度は外出しましょう」は、外にうようよしている「得体の知れないたんぱく質」への耐性づくりの上でも、理にかなっている。
「得体の知れないたんぱく質」は、日々、更新されている。
大多数の人は仕事で毎日、外気にさらされるけど、基本、在宅の人は、外気導入を意識する必要がある。
地域による個性
「得体の知れないたんぱく質」は、科学的に解明されているものも、そうでないものもある。
バリエーションは無数。
地域ごとの個性もある。
よく、新しい地で暮らすと、これまでにはなかった体調不良に、見舞われることがある。
(私の印象では、より温暖な気候の場所に移動した場合に多いような)
「水が合わない」と言われることもあるが、「得体の知れないたんぱく質」による影響じゃないかと思う。
引っ越し疲れとか、職場異動疲れもあると思うけど、それだけではないような…。
続きをごらんください 「得体の知れないたんぱく質」との共生





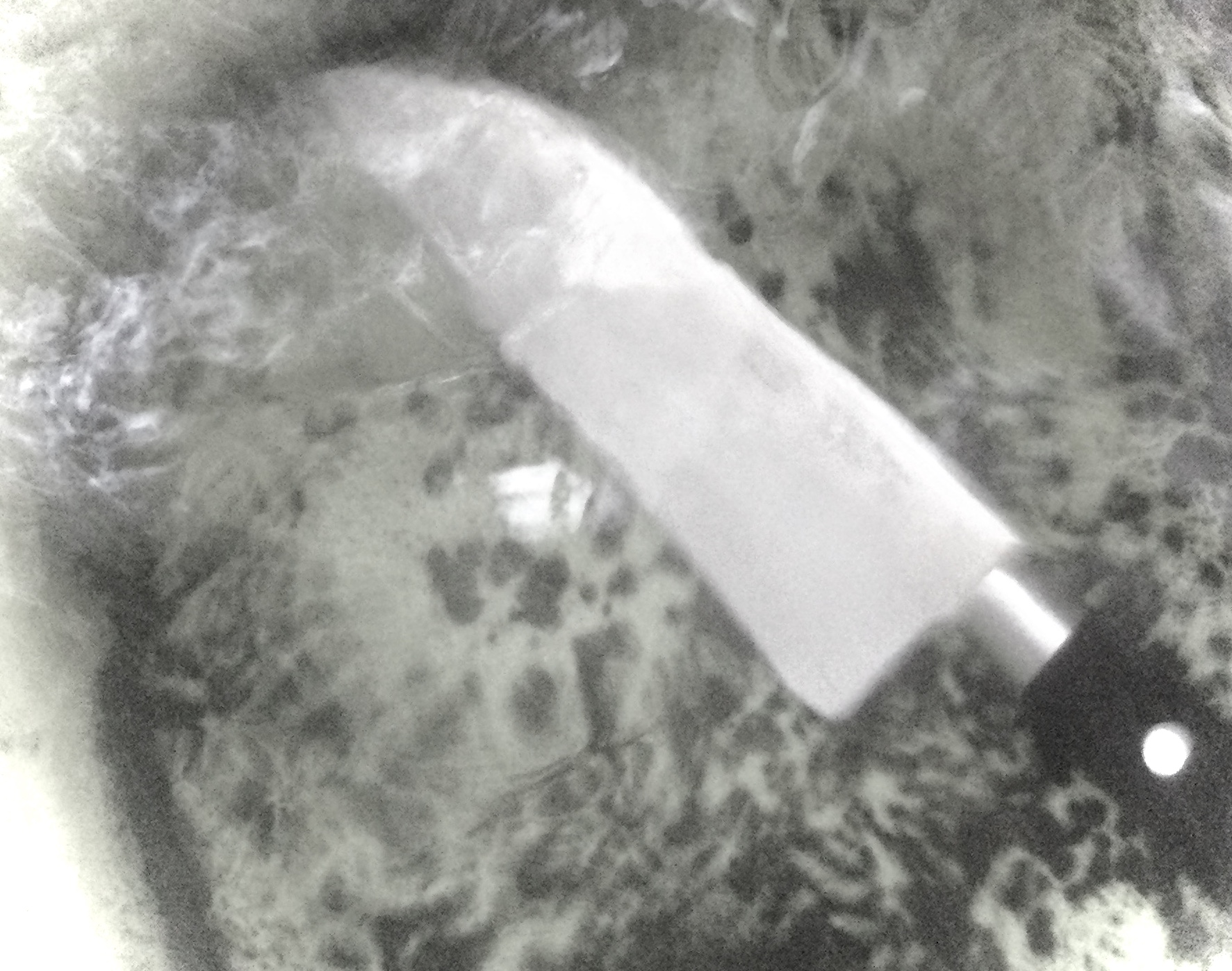


“「やっていいこと」を自分で決める” への1件のフィードバック